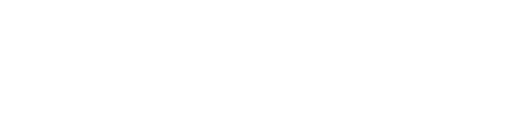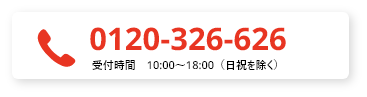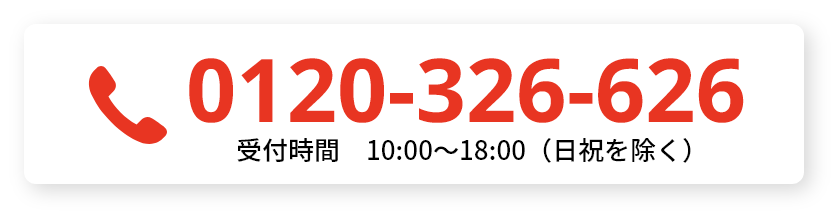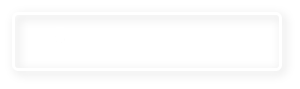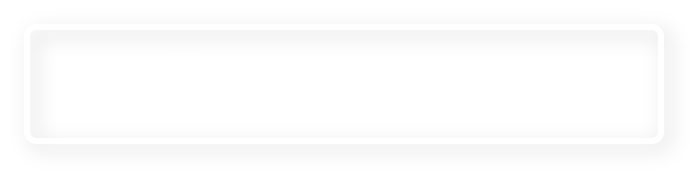この記事の目次
忍者ナインコラム
3歳におすすめの遊び9選!発達・発育別の遊びと注意点を解説
公開日:2025.04.10

「3歳とどんな遊びをすればいいかわからない」
「遊びを通して、どんな発達・発育を目指せばいいのだろう?」
「3歳の遊びで何に気をつければいいか知りたい」
3歳の子どもと時間を過ごすうえで、このような疑問点を抱えている人も多いのではないでしょうか。
3歳の子どもには「体を動かすこと」「言葉を覚えること」「社交性を身につけること」が必要です。そのため、だるまさんがころんだ・影踏み・絵本・かるた・ジェスチャーゲーム・ごっこ遊びなどをおすすめします。
この記事では、3歳におすすめしたい遊びの詳細や、子どもたちと遊ぶうえで気をつけたいポイントを解説します。子どものためになる遊びについて知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。
1. 3歳の遊びに必要なものとは?
発達・発育の面から考えると、3歳の子どもの遊びには「体を動かすこと」「言葉を覚えること」「社交性を身につけること」を盛り込むことが必要です。この段落では、上記の3点について詳しく解説します。

1-1. 体を動かすこと
3歳は、基礎的な運動能力が高まってくる時期です。そのため、遊びを通してたくさん体を動かし、さらに運動能力をアップさせることが求められます。
3歳の時期は「走る」「投げる」などの基本的な運動だけでなく、複雑な運動もできるようになってきます。「平均台の上を歩く」「友達とボール遊びができる」「遊具にぶら下がって遊べる」などが主な例です。
この時期になると、体幹を意識しながら自分の動きをコントロールしたり、全身を使った動きがスムーズに取れたりします。そのため、こういった発達を伸ばしてあげる遊びを提案しましょう。
1-2. 言葉を覚えること
3歳の遊びでは、言葉を用いることも重要です。3歳の子どもは、これまでに比べてたくさんの言葉を覚えるようになるからです。簡単な文章を使って自分の意思を伝えることもできるので、こういったスキルを引き出してあげましょう。
また、3歳は知的好奇心が旺盛になる時期でもあります。そのため、言葉を覚える楽しさやおもしろさを感じられる遊びを一緒にしてあげるとよいでしょう。
1-3. 社交性を身につけること
3歳になると、友達をはじめとした周囲の人々に対する社交性が高まっていきます。そのため、一人で完結する遊びではなく、友達とかかわりあえる遊びを経験することも重要です。
社交性の具体例としては、「ルールを守ること」「相手の気持ちを考えられるようになること」「善悪について認識できるようになること」などが挙げられるでしょう。
ルールを守りながら友達と協力するゲームや、助け合うことが求められる遊びを取り入れるのがおすすめです。そうすることで、さらに社交性を高められるでしょう。
2. 【発達・発育別】3歳におすすめの遊び9選
3歳の遊びに何が必要なのか理解できたところで、次は具体的な遊びの種類について見ていきましょう。今回は発達・発育の面から3つのタイプに分けて、全部で9つの遊びを紹介します。
なお、今回紹介している遊び方やルールはあくまで一例です。地域によって内容が変わることもあるので、あくまで参考としてご覧ください。

2-1. 体力や運動能力をつける遊び
まず取り上げるのは、子どもの体力や運動能力をアップさせる遊びです。全力で走り回ることによって基礎体力を高めたり、いろいろな姿勢をキープすることで体幹を鍛えたりする遊びをおすすめします。
今回は、その中でも「だるまさんがころんだ」「影踏み」「氷鬼」の3種類をピックアップしました。屋外だけでなく、室内でも遊べるものが多いので、状況に合わせて遊び場所を選んでみてくださいね。
2-1-1. だるまさんがころんだ
「だるまさんがころんだ」は、体のバランス感覚の向上が期待できます。基本的な遊び方は、以下のとおりです。
- 鬼役となった人が目印となる場所で自分の目を隠して「だるまさんがころんだ」と言う
- 「だるまさんがころんだ」と言い終わった鬼が振り返った瞬間に、他の人たちは体の動きをストップさせる。このときバランスを崩して転んだ・動いてしまった場合などは、鬼につかまる
- 「だるまさんがころんだ」と言い終わる前に、鬼か鬼につかまった人の体を他の人がタッチできたら、つかまっていた人も含めて鬼以外の全員が走り出す
- 鬼が「ストップ!」と叫んだときに一番鬼の近くにいた人が、新しい鬼役となる
鬼の動きにすぐ対応しなければならないため、反射神経を高められるという点も「だるまさんがころんだ」の特徴です。
2-1-2. 影踏み
鬼ごっこの一種である「影踏み」で走り回ると、体力や基礎筋力をアップできます。一般的な鬼ごっこでは鬼が別の人をタッチすることで鬼役を交換しますが、影踏みでは「影を踏むこと」がタッチの役目を果たします。自分の影を物陰に隠すことで鬼役の交換を免れる裏ワザもあるので、「影っておもしろい!」という知的好奇心を刺激することも可能です。
ただし、「影踏み」は影の特性を使った遊びなので、天候がよい日のみの遊びとなることは注意しておきましょう。屋内や天気が悪い日は、一般的な鬼ごっこや、次に紹介する「氷鬼」を試してみてください。
2-1-3. 氷鬼
「氷鬼」も鬼ごっこの一種で、体を全力で動かせる遊びの一つです。しかし、鬼にタッチされた場合は鬼役を交代するのではなく、氷になってしまったかのように動きを止めなければならないところが特徴的です。
氷になってしまった人は、鬼ではない別の人から再度タッチしてもらえれば動けるようになります。このままゲームを続け、すべての人が氷になってしまったら鬼の勝ちです。
「氷鬼」のポイントは、氷になってしまった人をタッチすることで助けられるというゲーム性の高さです。「他の人たちを助けるにはどうすればいいのだろう?」と頭を働かせることになるため、体を動かしながら社会性も向上できるでしょう。
2-2. 言葉を覚えるスピードを上げる遊び
次に、新しい言葉を覚えるための手助けになる遊びを紹介します。多くの語彙を学べたり、自分の知っている言葉を思い出すきっかけになったりする遊びを選んでみましょう。
今回は、「絵本」「かるた」「しりとり」といった3つの遊びをピックアップしました。遊びを通して言葉に触れ合うことで、自分の気持ちを言葉で伝えるための知識やスキルが身につくはずです。
2-2-1. 絵本
絵本を読むことも、大事な遊びの一つです。保護者が読み聞かせてあげてもよいですし、子どもが一人で絵本を読める場合は一人読みでも構いません。物語に触れることで、その絵本に登場した言葉を新しく覚えられます。
絵本は、子どもが興味を示したものを選んであげれば基本的に問題ありません。しかし、社会規範(あいさつや身だしなみなど)をテーマにしている絵本などを選ぶと、今後のしつけにも役立つでしょう。
2-2-2. かるた
絵や文字が描かれた札を取り合うかるたは、遊びながら言葉を覚えられる有意義なゲームです。たとえば、絵札に描かれた動物や食べ物などの名前がわからなくても、「サメという動物はこんな見た目をしているんだ」「この食べ物はハヤシライスという名前なんだ」というように、知識をインプットできます。
ただし、対象年齢が高すぎるかるただと興味を示さない可能性があるので、3歳児向けの商品を使うとよいでしょう。
2-2-3. しりとり
しりとりでは、自分が今までに覚えた言葉の中から適切なものを選んで回答します。結果的に言葉のアウトプットができるため、言葉を扱うスキルがアップするでしょう。また、一緒にしりとりをする相手が自分の知らない言葉を答えていた場合、語彙力を高めるきっかけにもなります。
なお、「濁音や半濁音は気にしない」「他の人が答えていた言葉でも使ってOK」など3歳でもやりやすいルールに随時変更することもポイントです。そうすることで、無理なくしりとりを進められるようになります。
2-3. コミュニケーション能力を伸ばす遊び
最後に紹介するのは、社交性を高める要素の一つでもある「コミュニケーション能力」を伸ばす遊びです。友達と協力しながら進める遊びや、相手がどんな気持ちになるかを考える遊びをチョイスしましょう。
2-3-1. ジェスチャーゲーム
ジェスチャーゲームとは、出題者がお題をジェスチャーで表現し、回答者にその答えを当ててもらうゲームです。なお、答えのヒントを声に出すことはルール違反とされています。そのため、なるべく回答者に伝わりやすいようなジェスチャーを意識することが求められるでしょう。
出題者は回答者の気持ちを考えながらジェスチャーすることになるので、自然にコミュニケーション能力が伸びていきます。
2-3-2. ごっこ遊び
ごっこ遊びとは、特定のキャラクターや職業になりきって遊ぶことを指す言葉で、おままごとなどもごっこ遊びの一種に含まれます。
複数人でごっこ遊びをする場合、相手の行動や発言に沿って自分の対応を変える必要があります。そのため、社会生活では欠かせない柔軟性や協調性が培われるのです。自分たちでストーリーを即興で進めていくため、表現力や思考力も高められるでしょう。
2-3-3. 工作
工作も、コミュニケーション能力を高められる遊びの一つです。なぜなら友達や保護者と一緒に工作をする場合、作り方や道具の使い方をまわりの人に質問するケースが多いからです。
工作をするときは、みんなで遊べる簡単なおもちゃを作るとよいでしょう。そうすることで、「自分で作ったおもちゃで遊ぶ」という達成感を味わえます。3歳児でも作り方がわかりやすいシンプルなおもちゃを選びましょう。
3. 3歳の遊びの注意点・ポイントは?
ここまで3歳の子どもにおすすめしたい遊びを詳しく紹介してきましたが、子どもたちと遊ぶ際に気をつけるべきことがいくつか存在します。「安全性に気をつけること」「親の負担が大きい場合はスポーツ教室も検討すること」の2つを取り上げるので、参考にしてみてください。

3-1. 安全性に気をつける
まず、子どもたちがケガをしないように、安全性に配慮することが重要です。たとえば、「転倒を防止するために、まわりの障害物を片付けておくこと」「ハサミなどを使うときは、子ども向けのケガ防止タイプを使うこと」などが例に挙げられるでしょう。
また、もしものアクシデントが発生してもすぐに対応できるように、子どもたちから目を離さないことも大切です。危険な行動を見つけた場合は、すぐにやめさせるようにしましょう。
3-2. 親の負担が大きい場合はスポーツ教室も検討する
もし仕事や家事などと子どもの遊びを両立することが難しいなら、スポーツ教室に通わせて遊んでもらうことも一つのアイデアです。3歳児になるとさまざまな遊びができるようになりますが、保護者が常に遊びの相手をすることは大きな負担になってしまいます。
多くの教室ではただ子どもと遊ぶだけでなく、運動能力や思考力などを効果的に伸ばせるプログラムが用意されています。そのため、子どもの成長にもよい影響を与えられるでしょう。
なお、スポーツ教室にもさまざまな種類があるので、気になる教室を複数調べておき、その中から比較検討することをおすすめします。体験授業を実施している教室も多いため、積極的に参加してみましょう。
4. 3歳の遊びで悩んでいるなら「忍者ナイン」もおすすめ
3歳の子どもには、「だるまさんがころんだ」「絵本」「ジェスチャーゲーム」などの遊びをおすすめします。これらで遊ぶことで、体力、語彙力、コミュニケーション能力などを高められるでしょう。子どもの発育・発達をより高めたいなら、今回の記事で紹介した内容をぜひ取り入れてみてください。
なお、スポーツ教室を利用することも3歳の遊びでは有効となります。「忍者ナイン」は、幼児・小学生に向けたスポーツ教室です。さまざまなスポーツに応用できる9つの基本動作をもとに、子どもたちの運動神経を伸ばしていきます。3歳の遊びについて悩んでいる方は、「忍者ナイン」の利用もぜひ検討してみてください。

執筆者:子どもスポーツ教室 忍者ナイン編集部